2018年技能試験 前期
2018/05/15 22:39:41
2018年技能試験 前期
2018年技能試験 前期2018年技能試験 前期の出願期間も終了し受験票が届くのを待つ時期になりました。弊社お客様も数名それぞれの塗装技能士や塗料調色技能士を受験されます。
微力ながら、自分の体験を含めて金属塗装及び塗料調色技能士を受験されるお客様の予行演習をさせて頂きました。
皆さん熱心にトライして頂きました。金属塗装では工程の順序を間違えない事やラッカーパテの塗り方、理想の時間配分などを実感して頂き工程の精度向上を日々練習しなければと認識されました。調色を受験されるお客様に関しては、手調色の練習と判断等試験の準備が必要だねとなりました。
調色試験は、私自身4年ぐらい前に受験、合格したのですが以前も本ブログで書いたように判断等試験が出来ていなかったと思います。
おそらく要素試験(以前は判断等試験のことをこう言っていたような気が)は合格ギリギリだったと思います。ですので、お教えできないと断った上で、反省するとすれば日塗工見本帳などを使って絶対音感ならぬ絶対色感のようなものを習得するしかないのかなとお伝えしました。
色相の違い 明度の違い 彩度の違いは マンセル色票である日塗工見本帳が大変参考になると思います。
判断等試験での問題で、実物判断という設問があります。
実際の塗料を匂いを嗅いだり触ったりてどの樹脂塗料かを判断したり、有機溶剤を嗅ぎ分けて溶剤の種類を判定する設問があります。
塗料調色試験に合格された方は、塗料調色技能士と言われますが塗料調色現場においてこんな判断を求められるケースがあるのでしょうか。
現在、塗料を扱う現場では有機溶剤の取り扱いが非常に厳しくなり、暴露時間を最小限に、当然、有機溶剤を吸い込むことは厳禁です。健康診断も半年に一度実施され作業者の健康を守るという事業者の認識を厳しく求められています。
こんな設問は、現場の現状と離れていると思いますが、関係各位の皆様には宜しくご検討いただければ塗料業界ももっと活気が出るのではと個人的には思います。
コメント
コメントはありません

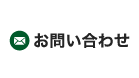




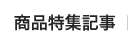
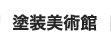

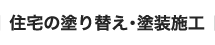





 RSS 2.0
RSS 2.0